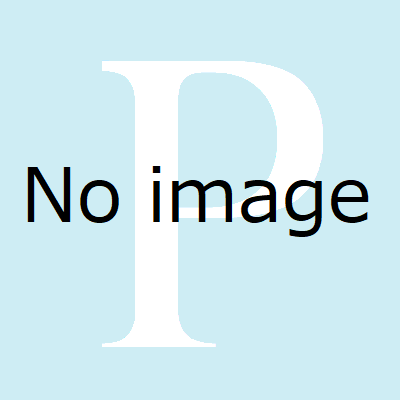水素原子を球対称な物体だとすると、その原子まわりの電子の波動関数については極座標で考えたほうが理解しやすいだろう。だが、それにはシュレディンガー方程式や波動関数を極座標に変換する必要がある。
この記事では、水素原子に含まれる電子の波動関数を、シュレディンガー方程式の極座標で表してみる。まず最初に、波動関数を角度方向成分と動径方向成分に変数分離する。その後、シュレディンガー方程式を利用して、それぞれの場合における波動関数を導出する。特に角度方向の波動関数は球面調和関数と呼ばれており、物理界隈では有名なものとなっている。
なお、極座標のシュレディンガー方程式に関するハミルトニアンについては、別記事でまとめてあります。
参考:極座標のシュレディンガー方程式に関するハミルトニアンの導出
3次元極座標のシュレディンガー方程式
極座標のラプラシアンは次の通りである。検索すればわかりやすい導出は出てくるため、ここでは導出は省く。
\begin{eqnarray}\Delta&=&\nabla ^2\\&=&\frac{\partial ^2}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial }{\partial r}+\frac{1}{r^2} \left( \frac{1}{sin \theta}\frac{\partial}{\partial \theta} \left( sin\theta\frac{\partial}{\partial \theta} \right) +\frac{1}{sin^2\theta}\frac{\partial ^2}{\partial \phi^2} \right)\\&=&\frac{\partial ^2}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial }{\partial r}+\frac{1}{r^2} A(\theta,\phi)\end{eqnarray}
ただし、この後動径方向成分\(r\)と角度方向成分\(\theta,\)\(\phi\)に変数分離することを考慮して、角度方向成分のラプラシアンを暫定的に\(A(\theta,\phi)\)とおいた。
このラプラシアンを使用すると、シュレディンガー方程式は次のように書き直せる。
$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{\partial ^2}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial }{\partial r}+\frac{1}{r^2} A(\theta,\phi) \right) +V({\bf r}) \right] \varphi(r,\theta,\phi) =E\varphi(r,\theta,\phi)$$
ただし、今回考えるポテンシャル\(V(r)\)は球対称で、原点からの距離\(r\)にのみ依存するものとした。
波動関数の変数分離
波動関数\(\varphi(r,\theta,\phi)\)を、動径方向成分\(r\)と角度方向成分\(\theta,\)\(\phi\)に変数分離する。
$$\varphi(r,\theta,\phi)=R(r)Y(\theta,\phi)$$
変数分離後の波動関数\(\varphi(r,\theta,\phi)\)を上のシュレディンガー方程式の左辺に代入する。
\begin{eqnarray}(左辺)&=&\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{\partial ^2}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial }{\partial r}+\frac{1}{r^2} A(\theta,\phi) \right) +V({\bf r}) \right] R(r)Y(\theta,\phi)\\&=&-\frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{\partial ^2}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial }{\partial r} \right) R(r)Y(\theta,\phi)-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} A(\theta,\phi) R(r)Y(\theta,\phi)+V({\bf r}) R(r)Y(\theta,\phi)\\&=&Y(\theta,\phi) \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{d^2}{dr^2}+\frac{2}{r}\frac{d}{dr} \right) \right] R(r)-R(r) \frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r^2} A(\theta,\phi) Y(\theta,\phi)+V({\bf r}) R(r)Y(\theta,\phi) \end{eqnarray}
これを元のシュレディンガー方程式に戻して、次のように変形させる。変数分離を考えるときは、分離させたい変数をそれぞれの辺に分けてやればよい。今回の場合は左辺に\(r\)、右辺に\(\theta,\)\(\phi\)を持ってくる。
$$Y(\theta,\phi) \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{d^2}{dr^2}+\frac{2}{r}\frac{d}{dr} \right) \right] R(r)-[E-V(r)]R(r)Y(\theta,\phi)=R(r) \frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} A(\theta,\phi) Y(\theta,\phi)$$
後は、両辺を\(R(r)Y(\theta,\phi)/r^2\)で割れば変数分離が完成する。ただし、ここでは\(\partial ^2/ \partial r^2\)の係数を1にして式を見やすくしたいため、両辺に
$$\times \left( -\frac{2m}{\hbar ^2}\frac{r^2}{R(r)Y(\theta,\phi)} \right)$$
をかけることにする。その結果は次式となる。
$$\frac{r^2}{R(r)} \left( \frac{d^2}{dr^2}+\frac{2}{r} \frac{d}{dr} \right) R(r)+\frac{2mr^2}{\hbar ^2}[E-V(r)]=-\frac{1}{Y(\theta,\phi)} A(\theta,\phi) Y(\theta,\phi)$$
以上で左辺は位置\(r\)、右辺は角度\(\theta,\phi\)の関数となり、変数分離が完成した。微分演算子がかかっているため、\(A(\theta,\phi) Y(\theta,\phi)\)は\(Y(\theta,\phi)\)で割っても消えないことに気をつけること。
上の式は、両関数がそれぞれの変数の値にかかわらず等しくなることを意味している。つまり、これらの変数にあらゆる数(ここでは正の実数しか入らないが)を代入しても、この関係は崩れない。したがって、左辺と右辺の値はこれらの変数\(r,\)\((\theta,\phi)\)によらない定数となる。ここではその値を定数\(l(l+1)\)として表す。この\(l\)について詳しくは後述する。
$$\left( \frac{d^2}{dr^2}+\frac{2}{r} \frac{d}{dr} \right) R(r)+\frac{2m}{\hbar ^2}[E-V(r)] R(r) =\frac{l(l+1)}{r^2}R(r)$$
$$-\frac{1}{Y(\theta,\phi)} A(\theta,\phi) Y(\theta,\phi)=l(l+1)$$
これで、変数分離によって求められる2式がでてきた。これからはそれぞれが満たす波動方程式\(R(r),\)\(Y(\theta,\phi)\)について考察する。
角度方向成分の波動方程式と球面調和関数の導出
まずは角度方向成分の波動関数\(Y(\theta,\phi)\)についての式を考える。
$$\frac{1}{Y(\theta,\phi)} A(\theta,\phi) Y(\theta,\phi)=-l(l+1)$$
変数分離
まだ上の式には2つの変数が残っているので、今度は\(\theta,\phi\)の変数分離を行う。
まず、\( Y(\theta,\phi)\)を
$$ Y(\theta,\phi)=\Theta(\theta)\Phi(\phi)$$
とおいて、元の方程式に代入する。後の変形は前の変数分離と同じである。
$$\left[ \frac{1}{sin \theta}\frac{\partial}{\partial \theta} \left( sin\theta\frac{\partial}{\partial \theta} \right) +\frac{1}{sin^2\theta}\frac{\partial ^2}{\partial \phi^2} \right] \left[ \Theta(\theta)\Phi(\phi) \right]=-\Theta(\theta)\Phi(\phi)l(l+1)$$
$$\Phi(\phi)\frac{1}{sin \theta}\frac{d}{d \theta} \left( sin\theta\frac{d}{d \theta} \Theta(\theta)\right)+\Theta(\theta)\frac{1}{sin^2\theta}\frac{d^2}{d \phi^2} \Phi(\phi)=-\Theta(\theta)\Phi(\phi)l(l+1)$$
$$\frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{sin \theta}\frac{d}{d \theta} \left( sin\theta\frac{d}{d \theta} \Theta(\theta)\right)+\frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{1}{sin^2\theta}\frac{d^2}{d \phi^2} \Phi(\phi)=-l(l+1)$$
$$\frac{1}{\Theta(\theta)} sin \theta \frac{d}{d \theta} \left( sin\theta\frac{d}{d \theta} \Theta(\theta)\right)+l(l+1)sin^2 \theta=-\frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{d^2}{d \phi^2} \Phi(\phi)$$
両変数をそれぞれの辺に分けられた。したがって両辺の値は、それぞれが含む変数\(\theta,\phi\)によらずに定数となる。今回はその定数を\(m^2\)とおく。
$$-\frac{1}{\Phi(\phi)} \frac{d^2}{d \phi^2} \Phi(\phi)=m^2$$
$$\frac{1}{\Theta(\theta)} \frac{1}{sin \theta} \frac{d}{d \theta} \left( sin\theta\frac{d}{d \theta} \Theta(\theta)\right)+l(l+1)=\frac{m^2}{sin^2 \theta}$$
\(\Phi(\phi)\)の求め方
磁気量子数mについて
まず、同半径で\(\phi\)に沿って一周すると同じ地点を指すことから、次の関係が成り立つことがわかる。
$$\Phi(\phi)=\Phi(\phi+2\pi)$$
この境界条件のもと、次の微分方程式を解く。
$$\frac{d^2}{d \phi^2} \Phi(\phi)=-m^2\Phi(\phi)$$
このような微分方程式の解は、\(Ce^{i \alpha \phi}\)という形になることが知られている。
したがって、これを\(\Phi(\phi)\)に代入すると、\(\alpha\)は
$$\alpha=\pm m$$
と求められる。さらに、前述した境界条件を満たすには次の2式
$$\Phi(0)=Ce^{i \alpha \cdot 0 }=C$$
$$\Phi(2\pi)=Ce^{i 2\pi \alpha}$$
が等しくなる必要があるから、\(\alpha\)は
$$1=e^{i 2\pi \alpha}$$
を満たす必要がある。\(e^{i2\pi (整数)}=1\)という複素関数の基本に注意すると、\(\alpha\)は整数だと言える。したがって、\(m\)もまた整数である。
$$m=0, \pm 1, \pm 2,…$$
このmのことを磁気量子数とよぶ。これは後述する方位量子数と並んで電子軌道を語るのに不可欠なものとなっている。
以上より、求める関数\(\Phi(\phi)\)は次のようになる。
$$\Phi(\phi)=Ce^{i2\pi m}$$
関数の規格化
次に関数\(\Phi(\phi)\)を規格化して、これに含まれる定数\(C\)を決定する。
存在確率(波動関数の絶対値の2乗)を全領域で積分すると1になることを利用すると、次の規格化条件がでてくる。
$$\int_0^{2\pi}|\Phi(\phi)|^2 d \phi=1$$
したがって、
\begin{eqnarray}1&=&\int_0^{2\pi}|\Phi(\phi)|^2 d \phi\\&=&\int_0^{2\pi} \Phi ^* (\phi) \Phi(\phi) d \phi\\&=&C^2 \int_0^{2\pi} e^{-i2\pi m} e^{i2\pi m} d \phi\\&=&C^2 \int_0^{2\pi} 1 \ d \phi\\&=&2 \pi C^2 \end{eqnarray}
だからCは
$$C=\sqrt{\frac{1}{2\pi}}$$
となる。ただし、規格化定数は正であることを考慮して負の方は除外した。
以上より、最終的な角度\(\phi\)方向の波動関数は次のようになる。
$$\Phi(\phi)=\sqrt{\frac{1}{2\pi}}e^{i2\pi m}$$
\(\Theta(\theta)\)の求め方と方位量子数について
$$\frac{1}{\Theta(\theta)} \frac{1}{sin \theta} \frac{d}{d \theta} \left( sin\theta\frac{d}{d \theta} \Theta(\theta)\right)+l(l+1)=\frac{m^2}{sin^2 \theta}$$
の両辺に\(\Theta(\theta)\)をかけて、さらに三角関数と微分に注意して変形させる。
$$\frac{1}{sin \theta} \left[ (sin \theta )’ \frac{d}{d \theta} \Theta(\theta) +sin\theta\frac{d^2}{d \theta ^2} \Theta(\theta)\right] +l(l+1) \Theta(\theta) =\frac{m^2}{sin^2 \theta}\Theta(\theta)$$
さらに変形させる。
$$\frac{cos \theta}{sin \theta} \frac{d}{d \theta} \Theta(\theta) +\frac{d^2}{d \theta ^2} \Theta(\theta) +l(l+1) \Theta(\theta) =\frac{m^2}{sin^2 \theta} \Theta(\theta)$$
ここで、\(x=cos \theta\)という変数変換を導入する。
$$\frac{d\Theta(\theta)}{d\theta}=\frac{dx}{d\theta}\frac{d\Theta(\theta)}{dx}=-sin \theta\frac{d\Theta(\theta)}{dx}$$
\begin{eqnarray}\frac{d^2\Theta(\theta)}{d\theta ^2}&=&\frac{d}{d\theta} \left( -sin \theta\frac{d\Theta(\theta)}{dx} \right)\\&=&-cos \theta \frac{d\Theta(\theta)}{dx} – sin \theta \frac{d}{d\theta}\frac{d\Theta(\theta)}{dx}\\&=&-cos \theta \frac{d\Theta(\theta)}{dx} + sin^2 \theta \frac{d^2\Theta(\theta)}{dx^2}\\&=&-cos \theta \frac{d\Theta(\theta)}{dx} + (1-x^2) \frac{d^2\Theta(\theta)}{dx^2}\end{eqnarray}
に注意すると、元の方程式は次のように変換される。
$$(1-x^2)\frac{d^2}{dx^2} \Theta(x)-2x\frac{d}{dx} \Theta(x) + \left( l(l+1)-\frac{m^2}{1-x^2} \right) \Theta(x)=0$$
この方程式はルジャンドルの陪微分方程式と呼ばれるもので、これの解は次のようになることが知られている。
$$\Theta(x)=C’ (1-x^2)^{\frac{m}{2}}\frac{1}{2^ll!}\frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}}(x^2-1)^l$$
ただし\(l\)は整数であり、\(m\)は
$$-l \leq m \leq l$$
を満たす。この\(l\)を方位量子数という。これを規格化したものが
$$\Theta(x)=\sqrt{\frac{2l+1}{2}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}} (1-x^2)^{\frac{m}{2}}\frac{1}{2^ll!}\frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}}(x^2-1)^l$$
また、規格化定数でない部分をルジャンドルの陪関数といい、\(P_l^m(x)\)で表す。
$$\Theta(cos \theta)=\sqrt{\frac{2l+1}{2}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(cos \theta)$$
球面調和関数の導出
球面調和関数\(Y(\theta,\phi)\)は
$$Y(\theta,\phi)=\Theta(\theta)\Phi(\phi)$$
であったから、これまでの結果を代入すればよい。
$$Y_l^m(\theta,\phi)=\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}} P_l^{|m|}(cos \theta)e^{im\phi}$$
ただし、磁気量子数\(m\)が負にもなりうることを考慮して、上の式では\(m\)の絶対値をとった。
動径方向の波動方程式
この節では\(F(r)\)や\(S(r)\)、\(f(r)\)、\(T(r)\)といった関数の定義が大量に出てくるため、どの関数についての式を変形しているのかを常に意識しながら読み進めること。
ポテンシャル\(V(r)\)について
原点(r=0)に存在する1個の陽子の周りに、1個の電子が存在しているような水素原子モデルを考える。電荷素量\(e\)と陽子-電子間の距離(原子半径)\(r\)を使うと、両者にはたらくクーロン力\(F(r)\)は次のようになる。
$$F(r)=-\frac{e^2}{4\pi \varepsilon _0}\frac{1}{r^2}$$
したがって、無限遠を0としたときに陽子がつくるポテンシャルは、次のように計算できる。
\begin{eqnarray}V(r)&=&-\int_{-\infty}^{r} F(r’)dr’\\&=&\frac{e^2}{4\pi \varepsilon _0}\int_{-\infty}^{r} \frac{1}{r’^2}dr’\\&=&\frac{e^2}{4\pi \varepsilon _0} \left[ -\frac{1}{r’} \right] _{-\infty}^{r}\\&=&-\frac{e^2}{4\pi \varepsilon _0}\frac{1}{r}\end{eqnarray}
参考:電場をクーロン力の式から定義する
動径方向のシュレディンガー方程式の変形
$$\left( \frac{d^2}{dr^2}+\frac{2}{r} \frac{d}{dr} \right) R(r)+\frac{2m}{\hbar ^2}[E-V(r)] R(r) =\frac{l(l+1)}{r^2}R(r)$$
まず方程式を簡単にするために、関数\(S(r)\)を
$$R(r)=\frac{S(r)}{r}$$
のように導入する。こうして\(S(r)\)に関する微分方程式に変換することで、微分演算子の数を減らすことができる。実際に微分を含む部分にこれを代入して、さらに微分公式
$$\left( \frac{f(x)}{g(x)} \right)’ =\frac{f’g-fg’}{g^2}$$
も使って確認してみる。
\begin{eqnarray}&&\left( \frac{d^2}{dr^2}+\frac{2}{r} \frac{d}{dr} \right) \frac{S(r)}{r}\\&=&\frac{d}{dr} \left[ \frac{1}{r^2}\left( \frac{dS}{dr} \cdot r -S \right) \right] +\frac{2}{r}\frac{1}{r^2}\left( \frac{dS}{dr} \cdot r -S \right)\\&=&\frac{d}{dr} \left[ r^{-1}\frac{dS}{dr}-r^{-2}S \right] +2r^{-2}\frac{dS}{dr}-2r^{-3}S\\&=&-r^{-2}\frac{dS}{dr}+r^{-1}\frac{d^2S}{dr^2}+2r^{-3}S-r^{-2}\frac{dS}{dr}+2r^{-2}\frac{dS}{dr}-2r^{-3}S\\&=&\frac{1}{r}\frac{d^2S}{dr^2} \end{eqnarray}
したがって、元の方程式は\(S(r)\)によって次のように変換される。
$$\frac{d^2S}{dr^2}+\frac{2m}{\hbar ^2}\left[ E+\frac{e^2}{4\pi \varepsilon _0}\frac{1}{r}\right] S(r) =\frac{l(l+1)}{r^2}S(r)$$
ただし、ポテンシャルV(r)には前述した水素原子の原子核(陽子1個)が作るポテンシャルを代入した。
ここでは式を見やすくするため、次の2文字
$$c^2 \equiv -\frac{2mE}{\hbar ^2}$$
$$\lambda \equiv \frac{me^2}{2\pi \hbar ^2 \varepsilon _0}$$
を導入して、方程式を書き換える。
$$\frac{d^2S}{dr^2}+\left[ -c^2+\frac{\lambda}{r}-\frac{l(l+1)}{r^2} \right] S(r) =0 \cdots (1)$$
今この微分方程式を解きたいわけだが、それにはまず境界条件を考える必要がある。そもそも波動関数とは粒子の存在確率を表しているので、原子核から十分遠い場所\((r \to \infty )\)では波動関数は0になることが予想できる。
$$S(r) \to 0 \ (r \to \infty)$$
この極限においては
$$\frac{1}{r}, \ \frac{1}{r^2} \to 0 \ (r \to \infty)$$
であるから、
$$\frac{d^2S}{dr^2}=c^2 S(r) \ (r \to \infty)$$
この方程式を満たす解は
$$S(r)=Ae^{+cr}+Be^{-cr}$$
が考えられるが、無限遠でS(r)が発散しないという境界条件を満たさなければならないことを考慮すると、
$$A=0$$
となる。したがって、関数\(S(r)\)の形は次のようになる。
$$S(r)=f(r)e^{-cr}$$
これを式(1)に代入する。
\begin{eqnarray}0&=&\frac{d^2}{dr^2}[f(r)e^{-cr}]+\left[ -c^2+\frac{\lambda}{r}-\frac{l(l+1)}{r^2} \right] (f(r)e^{-cr}) \\&=&\frac{d}{dr} \left[ \frac{df(r)}{dr} \cdot e^{-cr} + \frac{de^{-cr}}{dr} \cdot f(r) \right] +\left[ -c^2+\frac{\lambda}{r}-\frac{l(l+1)}{r^2} \right] (f(r)e^{-cr})\\&=&\frac{d^2f(r)}{dr^2} e^{-cr}-c \frac{df(r)}{dr} e^{-cr} +c^2 e^{-cr} f(r)-c e^{-cr} \frac{df(r)}{dr} +\left[ -c^2+\frac{\lambda}{r}-\frac{l(l+1)}{r^2} \right] (f(r)e^{-cr})\\&=&\frac{d^2f(r)}{dr^2} e^{-cr}-2c \frac{df(r)}{dr} e^{-cr} +\left[ \frac{\lambda}{r}-\frac{l(l+1)}{r^2} \right] (f(r)e^{-cr})\end{eqnarray}
最初の0と最後の式の両辺に\(e^{+cr}\)をかける。
$$\frac{d^2f(r)}{dr^2}-2c \frac{df(r)}{dr}+\left[ \frac{\lambda}{r}-\frac{l(l+1)}{r^2} \right] f(r)=0 \cdots (2)$$
最初の動径方向のシュレディンガー方程式がだいぶ見やすくなった。
\(y \equiv 2cr\)を使った式(2)の変形
変数\(y\)を次のように定義する。
$$y \equiv 2cr$$
これを使って、式(2)の変数rをyに置き換える。
$$\frac{df}{dr}=\frac{dy}{dr}\frac{df}{dy}=2c\frac{df}{dy}$$
$$\frac{d^2f}{dr^2}=2c\frac{d}{dr}\frac{df}{dy}=2c\frac{d}{dy}\frac{dy}{dr}\frac{df}{dy}=4c^2\frac{d^2f}{dy^2}$$
したがって、
$$4c^2 \frac{d^2f(y)}{dy^2}-4c^2 \frac{df(y)}{dy}+\left[ \frac{\lambda}{r}-\frac{l(l+1)}{r^2} \right] f(y)=0$$
両辺を\(4c^2\)で割る。
$$\frac{d^2f(y)}{dy^2}-\frac{df(y)}{dy}+\left[ \frac{\lambda}{2cy}-\frac{l(l+1)}{y^2} \right] f(y)=0 \cdots (2′)$$
関数\(T(y)\)の導入と\(f(y)\)に関する仮定
関数\(T(y)\)を次のように定義する。
\begin{eqnarray}T(y)&\equiv&a_0+a_1y+a_2y^2 \cdots +a_ny^{n}+\cdots \\&=&\sum_{n=0}^{\infty}a_ny^{n}\end{eqnarray}
さらに、今まで出てきた関数\(f(y)\)は、\(T(y)\)を使って次のように表せると仮定する。
\begin{eqnarray} \displaystyle f(y)&=&y^{l+1}T(y) \end{eqnarray}
この\(f(y)\)の1階微分と2階微分はそれぞれ
$$\frac{df(y)}{dy}=(l+1)y^lT(y)+y^{l+1} \frac{dT(y)}{dy}$$
$$\frac{d^2f(y)}{dy^2}=l(l+1)y^{l-1}T(y)+2(l+1)y^l \frac{dT(y)}{dy} +y^{l+1} \frac{d^2T(y)}{dy^2}$$
で表せるから、これを式(2′)に代入してみる。
\begin{eqnarray}&&\left[ l(l+1)y^{l-1}T(y)+2(l+1)y^l \frac{dT(y)}{dy} +y^{l+1} \frac{d^2T(y)}{dy^2} \right] \\ && \ -\left[ (l+1)y^lT(y)+y^{l+1} \frac{dT(y)}{dy} \right] +\left[ \frac{\lambda}{2cy}-\frac{l(l+1)}{y^2} \right] [y^{l+1}T(y)]=0\end{eqnarray}
\(T(y)\)のy微分ごとに整理する。
\begin{eqnarray}&&y^{l+1} \frac{d^2T(y)}{dy^2}+y^l[2(l+1)-y]\frac{dT(y)}{dy} \\ && \ +y^l \left[ \frac{l(l+1)}{y}-(l+1)+ \left( \frac{\lambda}{2cy}-\frac{l(l+1)}{y^2} \right) y \right] T(y)=0\end{eqnarray}
両辺を\(r^l\)で割る。
$$y \frac{d^2T(y)}{dy^2}+[2(l+1)-y]\frac{dT(y)}{dy}+ \left[ \frac{\lambda}{2c}-(l+1) \right] T(y)=0 \cdots (3)$$
ラゲール陪微分方程式と主量子数について
ラゲール陪微分方程式は、次のように定義される。
$$x\frac{d^2L_a^b(x)}{dx^2}+(b+1-x)\frac{dL_a^b(x)}{dx}+(a-b)L_a^b(x)=0 \cdots (4)$$
ただし、\(a=0,1,2,\cdots\),\( \ b=0,1,2,\cdots,a\)である。
そして、この微分方程式の解は次のようになることが知られている。
$$L_a^b(x)=\frac{d^b}{dx^b}\left[ e^x\frac{d^a}{dx^a}(x^ae^{-x}) \right]$$
これから、式(3)がラゲール陪微分方程式であることを示す。
まず、式(4)の第二項と、式(3)の最初の[]カッコ内を比較する。すると、式(3)の最初の[]カッコ内は、式(4)の第二項のbを
$$b \to 2l+1$$
と置き換えたものだということに気づくだろう。
次に、式(4)の第三項に、この関係を代入する。
\begin{eqnarray}a-b&=&a-(2l+1)\\&=&(a-l)-(l+1)\end{eqnarray}
この値と、式(3)の2つ目の[]カッコ内を比較すると、次の関係が見えてくる。
$$a-l=\frac{\lambda}{2c}$$
a,lはどちらも整数だから、\(\lambda / 2c\)も整数になる。ここで、この値をnと定義する。
$$n \equiv \frac{\lambda}{2c}$$
このnのことを主量子数(\(n=1,2,3,\cdots\))とよぶ。以上のことを踏まえて式(3)を書き換える。
$$y \frac{d^2T(y)}{dy^2}+[(2l+1)+1-y]\frac{dT(y)}{dy}+ \left[ (n+l)-(2l+1) \right] T(y)=0$$
これは明らかにラゲール陪微分方程式である。したがって、この解は
$$T(y)=L_{n+l}^{2l+1}(y)=\frac{d^{2l+1}}{dy^{2l+1}}\left[ e^y\frac{d^{n+l}}{dy^{n+l}}(y^{n+l}e^{-y}) \right]$$
となる。以上でようやく目的の波動関数を求める準備が整った。
動径方向の波動関数の導出
求める波動関数\(R(r)\)は、
\begin{eqnarray}R(r)&=&\frac{S(r)}{r}\\&=&\frac{f(r)e^{-cr}}{r}\end{eqnarray}
また、\(f(y)=y^{l+1}T(y)\)で、かつ\(y=2cr\)とおいたから、
$$f(y)=y^{l+1}T(y)=y^{l+1}L_{n+l}^{2l+1}(y)=(2cr)^{l+1}L_{n+l}^{2l+1}(2cr)$$
以上より、規格化定数を\(C”\)としたときの\(R(r)\)は
$$R(r)=C”(2c)^{l+1}r^lL_{n+l}^{2l+1}(2cr)e^{-cr}$$
また、これを規格化すると、
\begin{eqnarray}R(r)&=&\sqrt{2c \cdot \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}}(2c)^{l+1}r^lL_{n+l}^{2l+1}(2cr)e^{-cr}\\&=&\sqrt{\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}}(2c)^{l+\frac{3}{2}}r^lL_{n+l}^{2l+1}(2cr)e^{-cr}\end{eqnarray}
となる。
一応確認だが、式中の\(n\)と\(l\)は、それぞれ主量子数と方位量子数である。この方位量子数は、球面調和関数のときにでてきたものと同じである(変数分離のときにでてきた共通のパラメータだから)。
おまけ1:水素原子のエネルギー準位について
途中で
$$n \equiv \frac{\lambda}{2c}$$
という式が出てきたが、これに\(\lambda\)と\(c\)の定義式を代入したらどうなるだろうか。
\begin{eqnarray}n^2&=&\frac{\lambda^2}{4c^2}\\&=&\frac{m^2e^4}{4\pi^2\hbar^4\varepsilon_0^2} \cdot \left( -\frac{1}{4}\frac{\hbar^2}{2mE} \right)\\&=&-\frac{me^4}{32\pi^2\hbar^2\varepsilon_0^2E}\\&=&-\frac{me^4}{8h^2\varepsilon_0^2E}\end{eqnarray}
これをEについて解く。
$$E=-\frac{me^4}{8h^2\varepsilon_0^2n^2}$$
これは、電子の運動エネルギーとポテンシャルエネルギーから求めた電子のエネルギー準位と一致する。
参考:ボーア半径と水素原子のエネルギー準位の導出
おまけ2:有効ポテンシャルと遠心力ポテンシャル
最初の動径のシュレディンガー方程式を
$$\left( -\frac{\hbar ^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x) \right) \varphi (x)=E\varphi (x)$$
に近い形に直す。
$$\left[ – \frac{\hbar ^2}{2m} \left( \frac{\partial ^2}{\partial r^2}+\frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) +\left( V(r)+\frac{\hbar ^2 l(l+1)}{2mr^2} \right) \right] R(r)=ER(r)$$
上の2式を比較すると、極座標のシュレディンガー方程式のポテンシャルに対応する部分\(U(r)\)は
$$U(r)=V(r)+\frac{\hbar ^2 l(l+1)}{2mr^2}$$
となる。つまり、本来のポテンシャル\(V(r)\)に方位量子数\(l\)を含む項(遠心力ポテンシャルという)が加わっているのである。さらに、これらの和\(U(r)\)のことを有効ポテンシャルという。
波動関数の形について
ここまで、角度方向成分の波動関数\(Y(\theta,\phi)\)と、動径方向成分の波動関数\(R(r)\)の導出を見てきた。これらの具体的な形は適切な量子数n,l,mを代入すれば求まるが、数式だけでは波動関数の概形を直感的に理解することは難しい。
もし概形に興味がある場合は、下のホームページを見てみよう。そこでは水素原子の原子軌道だけでなく、様々な原子の電子軌道の概形が見れる。
参考(外部):周期表 (Japanese Periodic Table) – Orbital
まとめ
・波動関数を角度方向成分と動径方向成分に変数分離することで、それぞれの場合の波動関数を求めた。
・角度方向成分の波動関数の導出にはルジャンドルの陪微分方程式、動径方向成分の波動関数の導出にはラゲール陪微分方程式という有名な方程式が現れる。
・主量子数n、方位量子数l、磁気量子数mは、波動関数の形に大きく関わっている。
参考文献
原田勲・杉山忠男(2009)『講談社基礎物理学シリーズ6 量子力学I』,講談社.
二宮正夫・杉野文彦・杉山忠男(2010)『講談社基礎物理学シリーズ7 量子力学II』,講談社.
村上雅人(2006)『なるほど量子力学II』,海鳴社.
この『なるほど量子力学II』には、このページで省略した波動関数の規格化や、ルジャンドルの陪微分方程式の解き方などが書いてある。もし大学の課題などで出てきたら図書館などでこの本を探してみよう。