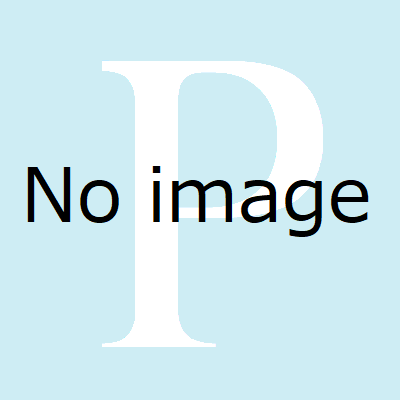原子核のまわりに存在する電子は、軌道角運動量・スピン角運動量という2種類の角運動量をもつ。この2つの角運動量の和が、電子の総角運動量ということになる。
この記事では、これら2つの角運動量の概要を解説する。
目次
原子の古典モデルと2種類の角運動量
注意
古典物理のスケールに住んでいる人間にとっては、量子力学のスケールの現象であるスピンを想像することは難しい。そこで、そのイメージをつけやすくするため、ここでは無理やり原子を古典的に表して考えることにする。
そもそもスピンは、後述するように古典近似で0になってしまう。そのため、本来はこのように古典的なモデルとして考えること自体ナンセンスだろう。ただし、ここでは最初にスピンに触れる方にイメージをつかんでもらうために、あえてこの古典的なモデルを引き合いに出した。この節に書いてある古典的なモデルは正確には間違っていることに注意すること。
電子の自転と公転

軌道角運動量は、電子の円運動による角運動量を指す。惑星で例えると公転に対応する。ただし、本来電子は原子核の周りに存在確率として分布しているものであり、原子核の周囲を円運動しているものではない。事実、もし本当に電子が円運動していると仮定すると、その電子は加速度運動によってエネルギーを放出し続ける(円運動は加速度運動である)ため、最終的には原子はつぶれてしまうことになる(参考:原子の構造)。
一方のスピン角運動量は、電子そのものが持つ角運動量のことである。この角運動量は電子の移動によって発生するものではないため、惑星の自転による角運動量のようなものと考えればわかりやすいだろう。
軌道角運動量について
古典力学における角運動量の復習
古典力学における角運動量は、次のように定義された。
これを、原子核の周り円運動するものと仮定した場合の電子に当てはめてみる。
角運動量演算子の導出
運動量演算子
を上の角運動量の定義に代入することで、角運動量演算子\(\hat{L}\)は次のように求まる。
参考:内積・外積の用途
角運動量演算子\(\hat{\bf L}\)のx軸,y軸,z軸成分をそれぞれ\(\hat{L}_x\),\(\hat{L}_y\),\(\hat{L}_z\)とすると、
軌道角運動量が満たすべき固有方程式
z軸方向の軌道角運動量演算子\(\hat{L}_z\)と、軌道角運動量演算子の2乗\(\hat{\bf L}^2\)は、それぞれ次の固有方程式を満たす。\(Y(θ,φ)\)は球面調和関数というもので、詳細は後述する。導出は別記事を予定している。
この式から、\(\hat{L}_z\)の固有値は\(mħ\)、\(\hat{\bf L}^2\)の固有値は\(l(l+1)ħ^2\)となる。したがって、角運動量の大きさ\(|L|\)の大きさは、
古典近似(\(ħ \to 0\))をとると、\(|L|\)は0になる。
ここで、式中の\(l\)と\(m\)は、それぞれ方位量子数と磁気量子数である。
高校化学ではs軌道、p軌道、d軌道といった電子の軌道を学んだと思うが、電子がどの軌道に属しているかで方位量子数が決まっている。例えば、\(l=0\)ならばs軌道、\(l=1\)ならばp軌道、\(l=2\)ならばd軌道である。
状態の縮退について
上の磁気量子数の定義から、磁気量子数\(m\)の数は\(2l+1\)個になる。例えば、\(l=2\)ならば、\(m=0, \pm 1, \pm2\)の5つとなる。つまり、電子のエネルギー準位は\(2l+1\)重に縮退しているといえる。このエネルギー準位の縮退は、電子に外部磁場が働いていないときのみ現れる。つまり、もし外部磁場が電子に働いている場合、この縮退が解けて、エネルギー準位が\(2l+1\)個に分裂する。この現象のことをゼーマン分裂とよぶ。
球面調和関数について
\(Y(θ,φ)\)は球面調和関数と呼ばれるもので、波動関数を極座標で表したときの角度成分を表す。
上の式中の\(P^m_l(cosθ)\)はルジャンドル陪関数というもので、ルジャンドル関数\(P_l(cosθ)\)を使うと
一見かなり複雑な数式で気後れするかもしれないが、前述したとおりにその意味は大して難しくない。
スピン角運動量
スピン角運動量とは、電子のような素粒子そのものが内在しているような角運動量のことである。スピン角運動量演算子は、記号で\(\hat{\bf S}\)と表される。
スピン角運動量の固有方程式
軌道角運動量で固有方程式ができたのならば、スピン角運動量でも似たような固有方程式が考えられるのではないだろうか。
スピン角運動量\(s\)が前節の方位角運動量\(l\)に対応しているとすると、このスピン角運動量も、軌道角運動量と同様に\(2s+1\)個のエネルギー準位が縮退しているとみなせる。ところが、電子のスピンには上向きスピンと下向きスピンの2準位しか存在しない。そのため、次の関係が成り立つ。
これをsについて解くと、
この場合、スピン量子数に対応する磁気量子数mは
このことと、スピン演算子を\(\hat{\bf S}\)としたときの固有方程式
を組み合わせると、この固有方程式の固有値は\(\pm ħ/2\)となり、次の関係が成り立つ。
古典近似(\(ħ \to 0\))をとると、\(S_z\)も0になる。
素粒子の種類とスピンの大きさ
今回考えた電子のスピン量子数は\(s=1/2\)であったが、これは素粒子の種類によって異なる。
電子のようにスピン量子数が半整数(1/2, 3/2,…)となる粒子をフェルミ粒子、一方整数となる粒子をボソン粒子という。
参考:大分配関数によるフェルミ粒子とボーズ粒子の分布関数の導出
全角運動量
軌道角運動量とスピン角運動量の和を、全角運動量とよぶ。この全角運動量\({\bf J}\)は、角運動量保存則によって保存される。
まとめ
・軌道角運動量とスピン角運動量は、惑星に例えるとそれぞれ公転と自転による角運動量に対応する。
・古典力学での角運動量の定義から、x,y,z成分ごとの軌道角運動量演算子を求めた。
・スピン角運動量の概要を解説した。
・軌道角運動量とスピン角運動量の和は、角運動量保存則によって保存される。
参考文献
原田勲・杉山忠男(2009)『講談社基礎物理学シリーズ6 量子力学I』,講談社.
二宮正夫・杉野文彦・杉山忠男(2010)『講談社基礎物理学シリーズ7 量子力学II』,講談社.
村上雅人(2006)『なるほど量子力学II』,海鳴社.