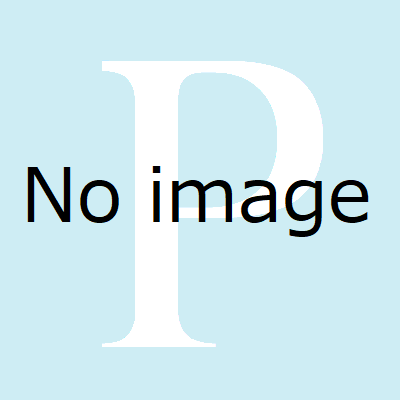確率流密度\({\bf j}\)とは、粒子が存在する確率の流れを表すベクトルであり、次のように定義される。
$$ {\bf j}({\bf r},t)=\frac{\hbar}{2mi}(ψ^*({\bf r},t)∇ψ({\bf r},t)-(∇ψ^*({\bf r},t))ψ({\bf r},t))$$
Bornの確率解釈
Bornは、今までの電子についての実験結果から、シュレディンガー方程式の波動関数に次のような条件付けを行った。
状態\(ψ({\bf r},t)\)において、時刻\(t\)に電子の位置を測定する。このとき\(r\)を含む\(d^3r\)内で電子が発見される確率は、次に比例する。ただし、\(ρ({\bf r},t)\)を確率密度とする。
$$ρ({\bf r},t)d^3r=|ψ({\bf r},t)|^2d^3r$$
参考:シュレディンガー方程式を解く意味とは
そして、確率を全範囲で積分すると\(1\)になるから、もし上式の積分を次のように規格化できたら、\(|ψ({\bf r},t)|^2\)は位置\({\bf r}\)に電子が発見される絶対確率密度となる。
$$\int |ψ({\bf r},t)|^2 d^3r=1・・・(1)$$
確率流密度\({\bf j}\)の導出
確率密度\(|ψ({\bf r},t)|\)の時間微分
\(|ψ({\bf r},t)|^2\)が絶対確率密度を示すことを証明したい。そのためには、時刻\(t\)がどのような値でも式(1)を満たさなくてはいけない。このことは、式(1)の左辺が\(t\)に依存しないと言い換えることができる。したがって、\(|ψ({\bf r},t)|^2\)が絶対確率密度であることを証明するためには、式(1)の左辺を\(t\)で微分して、その結果が0になることを確認すればよい。
では、実際に式(1)の左辺を\(t\)で微分してみる。
\begin{eqnarray} \frac{d}{dt}\int |ψ({\bf r},t)|^2 d^3r&=&\frac{d}{dt}\int ψ^*ψ d^3r\\&=&\int \left( \frac{∂ψ^*}{∂t}ψ+ψ^*\frac{∂ψ}{∂t} \right) d^3r \end{eqnarray}
ここで、次の2つのシュレディンガー方程式を思い出す。
$$\left( -\frac{ħ^2}{2m}∇^2 +V({\bf r}) \right) ψ({\bf r},t)=iħ\frac{∂}{∂t}ψ({\bf r},t)$$
$$\left( -\frac{ħ^2}{2m}∇^2 +V({\bf r}) \right) ψ^*({\bf r},t)=-iħ\frac{∂}{∂t}ψ^*({\bf r},t)$$
この2つをそれぞれ\(\frac{∂ψ}{∂t}\)と\(\frac{∂ψ^*}{∂t}\)について解いて、途中式に代入する。
\begin{eqnarray} \frac{d}{dt}\int |ψ({\bf r},t)|^2 d^3r&=&\int \left( \frac{∂ψ^*}{∂t}ψ+ψ^*\frac{∂ψ}{∂t} \right) d^3r\\&=&\int \left( -\frac{1}{i\hbar}\left(-\frac{ħ^2}{2m}∇^2 +V \right) ψ^*ψ+ψ^*\frac{1}{i\hbar}\left( -\frac{ħ^2}{2m}∇^2 +V \right) ψ \right) d^3r\\&=& \frac{\hbar^2}{2mi\hbar} \int \left( (∇^2ψ^*)ψ-ψ^*∇^2ψ \right) d^3r\\&=& -\frac{\hbar}{2mi} \int \left( ψ^*∇^2ψ-(∇^2ψ^*)ψ \right) d^3r\\&=&-\frac{\hbar}{2mi} \int \left( (∇ψ^*)∇ψ+ψ^*∇^2ψ-(∇^2ψ^*)ψ-(∇ψ^*)∇ψ \right)d^3r\\&=&-\frac{\hbar}{2mi} \int ∇・\left( ψ^*∇ψ-(∇ψ^*)ψ \right)d^3r\\&=&-\frac{\hbar}{2mi} \int_S \left( ψ^*∇ψ-(∇ψ^*)ψ \right)dS \end{eqnarray}
ただし、最後の変形でガウスの定理を使った。
ベクトル\({\bf j}\)の定義
ここで、ベクトル\({\bf j}\)を次のように定義する。
$${\bf j}({\bf r},t)=\frac{\hbar}{2mi}(ψ^*({\bf r},t)∇ψ({\bf r},t)-(∇ψ^*({\bf r},t))ψ({\bf r},t))$$
これを途中式に代入すると、
\begin{eqnarray} \frac{d}{dt}\int |ψ({\bf r},t)|^2 d^3r&=&-\int ∇・{\bf j}d^3r\\&=&-\int_S {\bf j}・{\bf n}dS \end{eqnarray}
波動関数\(ψ\)を波束とすると、\(ψ\)は十分遠方で0となるから、
$$-\int_S {\bf j}・{\bf n}dS=0(S→∞)$$
したがって、
$$\frac{d}{dt}\int |ψ({\bf r},t)|^2 d^3r=0$$
両辺を\(t\)で積分する。
$$\int |ψ({\bf r},t)|^2 d^3r=(tによらない定数)$$
この式を\(t=0\)で\(\int |ψ({\bf r},t)|^2 d^3r=1\)と規格化すると、時刻\(t\)がどのような値でも、積分値は1になる。
このように規格化できるため、Bornの確率解釈は正しい。
連続の式
\(\frac{d}{dt}\int |ψ({\bf r},t)|^2 d^3r\)の計算を途中で打ち切ってみる。
$$\frac{d}{dt}\int |ψ({\bf r},t)|^2 d^3r=-\int ∇・{\bf j}d^3r$$
ここまでの変形は、積分がなくても同じようにできる。確率密度を\(ρ({\bf r},t)=|ψ({\bf r},t)|^2\)と置くと、
$$\frac{dρ}{dt}=-∇・{\bf j}$$
この式は、湧き出しや吸い込みがない、密度\(ρ\)、流れ\({\bf j}\)の流体の保存則である。したがって、ベクトル\({\bf j}\)は粒子の存在確率の流れの密度と解釈できる。
ちなみにこの連続の式は、\(ρ\)を電荷密度、\({\bf j}\)を電流密度とすれば、電荷保存則を表す式になる。
まとめ
・確率流密度\({\bf j}\)を定義することで、\(|ψ({\bf r},t)|^2\)が絶対確率密度と解釈できるようになる。
・連続の式を組み立てることで、\({\bf j}\)は存在確率の流れの密度と解釈できる。
参考文献
・猪木慶治・川合光(1994)『量子力学1 (KS物理専門書)』,講談社.